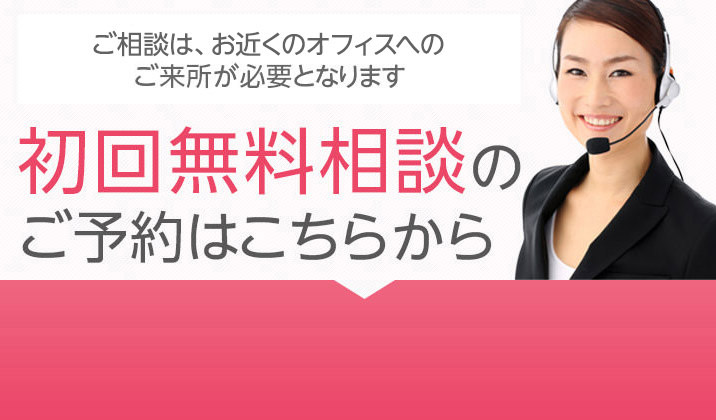子どもの認知手続きと養育費について|過去分の請求方法は?
- 養育費
- 養育費
- 認知

令和5年における「人口動態調査」によれば、婚姻している母親から生まれた子ども(嫡出子)の人数は709,428人(全体の97.5%)であるのに対し、婚姻していない母親から生まれた子ども(非嫡出子)の人数は、17,860人(全体の2.5%)です。
婚姻していない男性との間に子どもが生まれた場合、手続きをしなければ、その男性と子どもの間に法律上の親子関係(父子関係)が発生しません。法律上の親子関係を発生させるには、父親である男性に子どもを認知させる必要があります。また、父親が子どもを認知しているかどうかは、父親による養育費の支払いにも影響を与えます。
本コラムでは、認知と養育費の関係や、認知させる手続きについてベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。


1、認知とは?
「認知」とは、法律上の婚姻関係を結んでいない(結婚していない)男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)に、法律上の親子関係を発生させる手続きをいいます。
父親と非嫡出子が法律上の親子となるには、認知の手続きが必要となります。
認知には、「任意認知」と「強制認知」の2種類があります。
親が自発的に行う認知です。
生前に行う場合のほか、遺言による認知(民法第781条第2項)も認められています。
● 強制認知
家庭裁判所の審判または認知の訴えにおける判決に基づき、強制的に効果が生じる認知です。
親が死亡した場合でも、死後3年以内であれば強制認知を求めることができます(民法第787条)。
-
(1)嫡出推定制度
嫡出推定制度とは、生まれてきた子どもの父親を法律上推定する仕組みです。母子関係は出産という事実で明らかになりますが、父子関係は必ずしも明確ではないため、民法には推定規定が設けられています。
● 嫡出の推定
・妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定されます。女性が婚姻前に妊娠した子であっても、婚姻が成立した後に生まれた場合には、同様に夫の子と推定されます(民法第772条1項)。
・前項において、婚姻が成立した日から200日以内に生まれた子については、婚姻前に妊娠したと推定されます。また、婚姻成立から200日よりも後に生まれた子も婚姻中に妊娠したものと推定されます。また、離婚や婚姻取り消し後300日以内に生まれた子も、元夫の子と推定されます(同条2項)。
・第1項において、女性が子を妊娠してから出生するまでの間に2回以上結婚していた場合、その子は、その出生の直近で成立した婚姻の夫の子であると推定されます(同条3項)。
この嫡出推定により、子どもは生まれた時点から嫡出子としての身分を得て、父親からの扶養を受ける権利などが保障されることになるのです。
-
(2)認知によって生じる親子間の主な法律関係とメリット
父親が子を認知することで、法律上の親子関係が成立し、さまざまな権利義務が発生します。
特に重要なのが、扶養義務と相続権です。法律上の親子は直系血族として、互いに扶養する義務を負うため、子どもは父親に対して養育費の支払いを請求できます。
また、認知された子は、父親が亡くなった場合の相続人となり得ます。逆に、認知がなければ、血のつながりのある親子であっても、これらの権利・義務は発生しないのです。
さらに、子の戸籍には父親の氏名が記載されることになるため、法的な親子関係が公的に証明されることになります。認知をした父親を子の親権者に指定することもできます。
2、養育費をもらうには認知は必要?
認知をすれば養育費の支払い義務が発生しますが、認知がない場合には支払ってもらえるのでしょうか。
-
(1)合意があれば認知がなくても養育費を受け取れる
原則として、子の養育費の支払い方法は、両親の間の協議によって決定されます。
認知をしていなくても、両親の間で養育費の支払いを合意すれば、合意内容に基づいて養育費を支払う契約上の義務を負います。
したがって、父親が子を認知していなくても、父親との間で合意すれば、養育費を受け取ることが可能になります。 -
(2)父親が養育費の支払いを拒否する場合は認知が必要
父親が養育費の支払いを拒否する場合、最終的には審判手続きを通じて、裁判所に養育費の支払いを命じてもらう必要があります。
しかし、裁判所が父親の養育費の支払い義務を認めるのは、父親と子の間に法律上の親子関係が存在する場合のみです。
したがって、父親が拒否する養育費の支払いを受けるには、その前に認知の効力を発生させる必要がある点に注意してください。
お問い合わせください。
3、父親に子どもを認知させるための手続き
任意認知・強制認知は、それぞれ以下の手続きによって行います。
-
(1)任意認知の手続き
任意認知は、生前であれば戸籍法上の届け出によって行います。
認知をする親(父親)の本籍地の市区町村の窓口へ、認知届を提出しましょう。
また、認知をする旨と併せて養育費の支払いについても取り決め、公正証書の形で合意書を締結しておくことをおすすめします。
なお、子が成年(18歳以上)である場合には、子の承諾がなければ任意認知をすることができません。
また、胎児を認知する場合には母の承諾が必要であり、この場合は母の本籍地が届け出先となります。
一方で、任意認知は遺言によって行うこともできます。
遺言による認知があった場合、被相続人の本籍地の市区町村役場へ、認知があった旨を相続人が代理で届け出ましょう。 -
(2)強制認知の手続き
親が認知を拒否している場合、子と、子の直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。
また、認知の訴えは、親が死亡した場合でも死亡後3年以内であれば提起できます。
ただし、いきなり裁判で認知を訴えることはできないため、まずは家庭裁判所に「認知調停」を申し立てなければなりません。
認知調停においては、当事者間で親子関係がある旨の合意がされて、家庭裁判所が調査のうえでその合意を正当と認めれば、合意に相当する審判を行われます。
これに対して、認知調停で合意に相当する審判が行われなかった場合には、改めて認知の訴えを提起して、判決による認知を求めることになるのです。
審判または判決によって認知が確定したら、確定日から10日以内に、親の本籍地の市区町村役場に対して認知届を提出してください。
4、養育費は過去分も請求できる?
子の父親に対して養育費を請求する場合、いつの時点までさかのぼって請求できるかが問題となります。
一般的な離婚の事例は、請求時以降の養育費しか認められないことが大半です。
しかし、認知に伴う養育費の請求の場合には、出生時までさかのぼって養育費の支払いが認められるケースもあります。
-
(1)一般的な離婚のケース|請求時以降の養育費しか認められない
夫婦の離婚に伴い、非同居親から同居親に養育費を支払うケースでは、請求を行った時点以降の養育費に限って支払いが認められるのが原則です。
「扶養義務は抽象的な義務であり、具体的な請求権は協議等によって内容が確定した後に初めて発生する」という考え方から、このような取り扱いがなされています。 -
(2)認知のケース|出生時までさかのぼって養育費の支払いが認められた裁判例あり
これに対して、認知に伴い養育費を請求する場合、子の出生時にさかのぼって養育費の支払い義務を認定した裁判例があります(大阪高裁平成16年5月19日決定)。
認知のケースでは、認知の効力を確定させてから養育費を請求するという手順をふまなければなりません。
認知によって法律上の親子関係が発生した時点で、初めて養育費の支払い義務が発生するためです。
また、認知の効力は出生時にさかのぼって発生します(民法第784条)。
大阪高裁は、上記の法律上のルールを前提として、出生時にさかのぼって養育費の支払い義務を認めました。
大阪高裁が出生時以降の養育費の支払い義務を全面的に認めたのは、母親が迅速に認知・養育費の支払いを求める請求を行ったためであると考えられます。
養育費をできる限り長い期間受け取るには、早期に認知・養育費の支払いを求める手続きを取ることが大切といえるでしょう。
5、認知や養育費の請求について弁護士に相談するメリット
認知や養育費の請求は、手続きが複雑で、精神的な負担も大きいため、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、認知の請求や養育費の金額の交渉などは弁護士が代行するため、相手方と直接やり取りをする心理的負担を軽減できます。特に、父親が任意に認知に応じない場合の強制認知は、証拠の収集や調停・裁判手続きへの対応が必要となるため、弁護士によるサポートが不可欠です。
また、両親の収入バランスや子の人数・年齢などに応じて、適正額の養育費を支払ってもらいたい場合も、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、法的な根拠に基づいて養育費の金額を適切に算定したうえで、サポートが可能です。
弁護士は、認知の手続きや養育費の算定基準に関する専門的な知識・経験に基づき、適切な証拠の収集・書類作成、相手との交渉、裁判対応を行うため、スムーズな解決が期待できます。
お問い合わせください。
6、まとめ
婚姻外で生まれた子について、父親に養育費を請求したい場合には、父親との間で支払いにつき合意するか、または子が父親の認知を受けることが必要です。
特に父親が認知も養育費の支払いも拒否している場合には、認知調停・認知の訴え・養育費調停などの法的手続きを通じて請求を行う必要があります。
離婚や養育費に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスへご相談ください。弁護士は、これらの手続きを全面的に代行し、適正な養育費の獲得に向けて親身にサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています