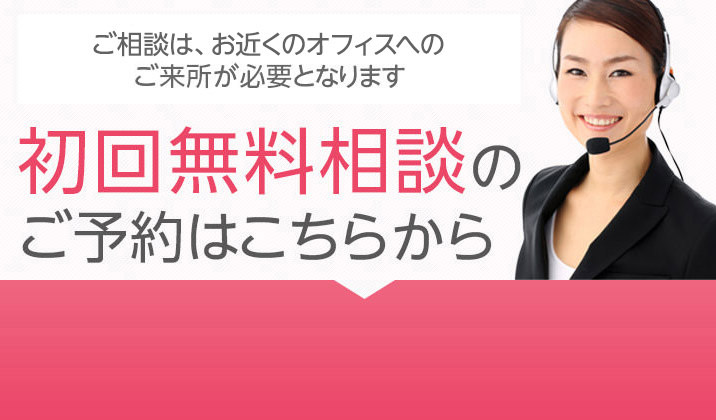離婚届の書き方と届け出方法とは? 提出前に準備しておくべきこと3つ
- 離婚
- 離婚
- 離婚届
- 弁護士
- 札幌

離婚が決まったら、すぐにでも離婚届を提出してすっきりしたいと考える方は多いでしょう。たとえば、札幌市内に住民票があるご夫婦であれば、札幌市役所に離婚届を提出することになります。
離婚届を出す前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができ、後々のトラブルを回避することができます。
本コラムでは、離婚届を提出する際に必要な書類などの準備から離婚前に決めておいたほうがよいことについて、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。


1、離婚届の入手方法や書き方
離婚届は市役所などへいくだけでなく、郵送などでも受け取れます。以下では離婚届の入手方法と提出先などについて解説します。
-
(1)離婚届の入手方法
離婚届は、市区町村役場などで入手することができます。離婚届は都道府県や市区によって様式が変わるものではなく、全国同じ書式なので、自分や配偶者の本籍地や住所地を管轄する自治体で入手する必要はありません。都合のよいところで手に入れましょう。
-
(2)近くで手に入らないとき
近くに市町村役場がない場合や、自宅からなかなか離れられない事情がある場合には、郵送やダウンロードでも入手することができます。
郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼ったものを区役所宛に送る必要がありますが、戸籍課や市民課など、送付先の課がどこになるかは自治体によって変わります。郵送で離婚届を入手する場合には、あらかじめ自治体に電話などでその旨を伝え、郵送先も確認しておきましょう。
離婚届はダウンロードすることも可能ですが、ダウンロードする際には、用紙サイズに注意が必要です。離婚届は婚姻届と同じく、A3サイズになっているため、ダウンロードしたものもA3サイズでプリントアウトする必要があります。
自宅にプリンターがない場合は、コンビニなどでも印刷することができます。 -
(3)離婚届の書き方
離婚届は以下のように記入します。
・届出年月日
離婚届を実際に提出する日を記入します。提出する際に窓口で記入することもできます。
・氏名・生年月日
戸籍上の氏名を記載します。
・住所
住民登録をしている住所を記入します。
・本籍
婚姻中の本籍と戸籍の筆頭者の氏名を記入します。
・父母の氏名・父母との続き柄
実父母の氏名を記入します。父母がすでに死亡している場合も実父母の氏名を記入します。
続き柄には、長男、次女などと記載します。
・離婚の種別
該当する離婚の種別にチェックを入れます。
・婚姻前の氏に戻る者の本籍
離婚によって氏が戻る方は、該当するものにチェックを入れます。
ただし、現在の氏を離婚後も使用したい場合には記入はせず、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
・成年の子の氏名
夫婦に未成年の子どもがいる場合には、夫または妻のいずれかを親権者と定めて記入します。
・同居の期間
同居を始めた年月と別居をした年月を記入します。
・別居する前の住所
離婚届を提出する時点で夫婦が別居をしている場合には、同居していた際の住所を記入します。
・別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
国勢調査をする年の4月1日から翌年3月31日までに離婚届を提出する場合のみ記入します。
・その他
養父母がいる場合には、「その他」の欄に養父母の氏名、続き柄を記入します。
・届出人署名押印
夫婦それぞれが署名し、別々の印鑑で押印します。
・証人
協議離婚の場合には成人2人の証人が必要です。「証人」の欄は証人本人が署名し、別々の印鑑で押印します。 -
(4)離婚届の提出先
離婚届は、夫婦の本籍地か所在地の市区町村役場に提出しなければなりません。
調停離婚ではなく裁判離婚の場合は、夫婦ではなく届出人の住所地の区役所等でも提出は可能です。本籍地と所在地のどちらで離婚届を出そうか迷っている場合には、本籍地の市町村役場に提出することをおすすめします。
本籍地以外の市区町村役場で離婚届を提出するときには、添付書類として戸籍謄本、または全部事項証明書が必要となるためです。必要書類については、後ほど解説します。
2、離婚届を提出する際に必要な書類
離婚の形態としては、協議離婚や調停離婚、裁判離婚などがありますが、それぞれに添付書類が異なります。
添付書類がなければ、離婚届の受理に手間がかかってしまう可能性もあるため、添付書類について確認しておきましょう。
-
(1)本籍地と同じ市町村役場で協議離婚届を提出する
夫婦の本籍地を管轄する市町村役場で協議離婚の離婚届を提出する場合に必要なものとしては、離婚届の他に夫婦の印鑑と身分証明書です。夫婦である間は同じ名字ですが、同じ名字であっても別の印鑑が必要ですので注意しましょう。
また、あらかじめ離婚届を書いて押印していたとしても、不備があった場合にはその場で訂正し、捨て印を押印する必要が出てきます。そのため、印鑑は準備しておきましょう。 -
(2)本籍地ではない市区町村役場に提出する場合
夫婦の本籍地ではない市区町村役場、または離婚後の本籍地とは別の市区町村役場に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本、または戸籍の全部事項証明書を添付する必要があります。
-
(3)協議離婚以外の離婚の場合
協議離婚の他に、調停離婚や裁判による離婚では以下の書類が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本、確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本、確定証明書
3、離婚届の提出前に確認しておきたい注意点
離婚届に空欄がある場合、不備があるものとして離婚届を受付されないこともあります。必要事項はしっかりと記入するようにしましょう。
-
(1)証人の署名と押印(2人)
協議離婚の場合には、20歳以上の成年者を2名証人に立てる必要があります。離婚届には、その2人から署名と押印をもらわなければなりません。
夫婦どちらかの両親に証人に立ってもらう場合には、2人の名字は同じになりますが、こちらも印鑑は別々のものが必要です。 -
(2)除籍後の戸籍について
離婚届を記入するときには、除籍した人が除籍後に自分の戸籍をどこに定めるかまで記載する欄があります。選択肢は2つで、両親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者として新しく戸籍を作るかになります。
日本では、ほとんどの夫婦が結婚するときに男性の戸籍に女性が入ります。そのため、多くの場合は、女性が離婚後の籍をどうするか記載することになります。 -
(3)未成年の子どもがいる場合、親権者の記載が必要
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもの親権を夫婦のどちらが有するかを離婚届に記載しなければなりません。この記載がなければ、離婚届は受理されません。
-
(4)離婚届を書き間違えたとき
離婚届を書き損じた場合は二重線を引き、捨て印を押せば問題ありません。ただし、修正液を使うのはNGですので、この点は注意しておきましょう。
4、離婚届が受理されないケースとは
離婚届が受理されないケースについて紹介します。
-
(1)記載に不備がある場合
未成年の子どもがいるのに親権者が決まっていなかったり、除籍する人のその後の戸籍が記載されていなかったりと、記載そのものに不備がある場合には、受理されないことがあります。
単なる書き忘れであれば、その場で追記すれば問題ありません。しかし、証人の署名がないなど、その場で修正ができないときには、改めて提出するよう求められることになります。
離婚届の記載例には注意点も記載されているため、参考にしながら書くと漏れがなくなるでしょう。 -
(2)相手から不受理申出書が出されている場合
離婚届そのものに形式的な不備がなくても、夫婦の一方が「離婚届不受理申出」をしている場合は、離婚届が受理されません。
不受理申出とは、いったんは離婚届に署名押印をしたが、その後気が変わり、離婚届を出されることを阻止したいというような場合に使われる手続きです。
不受理申出には有効期限がないため、取り下げない限りは離婚届が受理されないことになります。
5、離婚前に準備しておきたいこと
離婚届が受理されてしまったら、それを覆すことは困難です。また、夫婦といえども離婚後は他人になるため、容易に連絡が取れなくなるでしょう。離婚後に「もっと話し合っておけばよかった」「もっと準備しておけばよかった」と後悔することを少しでも減らすために、離婚前に準備しておきたいことを解説します。
-
(1)財産分与や親権などについて
子どもがいる場合は親権者に加え、養育費や面会交流権について詳しい取り決めをしておく必要があります。
また、夫婦でいる間に得た夫婦の共有財産については、財産分与をして、離婚後に財産が夫婦のどちらに属するかを決める必要があります。この他にも、慰謝料や年金分割など、離婚時に取り決めておくべきお金のことは多いものです。
親権以外は離婚前に必ず決める必要があるものではないため、「面倒な話し合いは離婚して落ち着いてからでいいや」「顔も見たくない」と、つい話し合いを先延ばしにしてしまいがちです。しかし、可能な限りこれらの重要な取り決めは、離婚前にしておくことが賢明です。
なぜなら、財産分与や養育費などの請求権は、離婚後一定期間請求せずに放置しておくと消滅時効にかかってしまうからです。請求権が時効で消滅してしまったら、権利を主張すること自体ができなくなります。
親権や養育費、財産分与や面会交流の話し合いでもめてしまうときは、弁護士に相談してください。あなたの代理人として相手方と交渉し、法的に適切な結果を得られるようサポートします。 -
(2)離婚協議書を作成しておく
養育費や財産分与について合意していても、口約束でとどめず、離婚協議書という文書に残しましょう。なかには、離婚さえできればいいと本意ではないことを約束してしまう人もいるかもしれません。離婚後に「そんなことを約束した覚えはない」などとシラを切られてしまっても、証拠がなければ泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
離婚時に約束したことは、できるだけ詳細に記載して離婚協議書に残しておきましょう。また、養育費や財産分与などの金銭に関係する約束は、強制執行認諾文言をつけた公正証書にしておくと安心です。万が一支払いが滞ったとき、速やかに手続きを行うことができます。 -
(3)離婚後にどんな手続きが必要か把握しておく
離婚後に旧姓に戻る場合には、預金やクレジットカードの名義を変更しなければなりません。また、扶養に入っていた場合には、扶養を抜ける手続きや、配偶者の厚生年金から自分の国民健康保険に変わる手続きなどが必要になります。
しかし、離婚後は何かとバタバタしてしまいがちです。特に専業主婦(夫)やパート勤務の場合は、離婚後の生活を軌道に乗せるのが大変な傾向があるため、忙しさに追われてそれらの手続きがおろそかになってしまうケースもあるようです。
あらかじめ、どのような手続きが必要になるのかは、個々の状況で異なります。離婚前もいろいろ大変ではありますが、離婚後の生活の負担を少しでも軽くするため、離婚後にどんな手続きが必要になるかを整理しておきましょう。
お問い合わせください。
6、まとめ
離婚届が受理されて夫婦関係が解消されてしまうと、それを覆すことは相当困難です。また、当然ですが、相手の了承を得ずに勝手にサインをして離婚届を提出することは、罪に問われる可能性がある行為なのでしてはいけません。
離婚後の暮らしをスムーズに始めるためにも、離婚前にできることはできるだけ準備しておくことをおすすめします。離婚の際に決めるべき、財産分与や養育費、親権、面会交流などが決まらずお悩みのときは、弁護士に相談してください。ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスでは、離婚時や離婚後に発生しがちなトラブルをできるだけ回避できるよう、将来を見据えて力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています