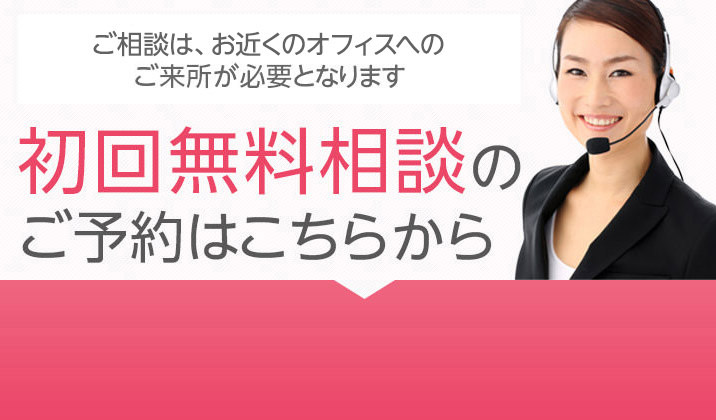旦那がストレスで離婚したい! 離婚方法や拒否された場合の対応
- 離婚
- 旦那
- ストレス
- 離婚

厚生労働省が公表している令和5年の「人口動態統計」によると、令和5年中の札幌市における離婚件数は3558件でした。
「旦那が家にいるだけでストレスを感じている」という方をテレビなどで「夫源病」と称したことから、一時期脚光を浴びました。札幌市にお住まいの方でも、いわゆる夫源病に悩まされて離婚したいと考える方はいらっしゃるでしょう。
しかし、ただ「離婚したい」という気持ちだけで行動を起こしてしまうと、たとえ離婚できたとしてもご自身にとって不利な条件での離婚となってしまう場合があります。離婚後に後悔しないようにするためにも、どのような行動ととるべきか、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。


1、「旦那がストレス」になりうる環境とは
「夫の言動が原因で、妻の体調が悪くなる」という症状に悩まされている方は少なくないようです。症状への気づきも人それぞれで、結婚後すぐに症状が出る方もいれば、夫の定年退職後に症状が悪化して病院でストレスだと診断されて初めて気づくという方もいるでしょう。
では、夫のどのような言動で妻はストレスを感じうるのか、実際に妻にどのような不調が起きるのか、早期発見のためにも具体的にみていきましょう。
●働きに出たいという妻に対して
「働きに行くなら、家事を完璧にこなしてからにしろ」
「稼ぎが少ないと言いたいのか?」
「ご飯には手を抜くな」「家事をおろそかにするな」などと、細かく言ってくる。
●体調が悪く体を休めたいと伝えた妻に対して
「俺のご飯はどうなるの?」
「俺の明日の出張準備は誰がするの?」など
「旦那がいるだけでストレス」と感じうる原因となる夫の言動には、モラハラにつながるような、妻をいたわらない見下した発言が多くみられるのが特徴です。
夫が家にいないときには心身ともに安らぎ、ホッとした気持ちになる反面、夫の帰宅時間が近づくとストレスを感じて「動機」「息切れ」「胃痛」「頭痛」「不眠」「躁鬱(そううつ)状態」などの症状が現れます。
更年期障害と勘違いしてしまい、そのまま我慢して悪化させているケースもあり、注意が必要です。
2、「旦那がストレス」を理由に離婚をする方法
旦那のストレスを理由に離婚する場合には、次の方法があります。
-
(1)夫婦で話し合う(協議離婚)
夫婦が話し合い、双方が納得したうえでおこなう「協議離婚」の場合には、離婚理由にかかわらず離婚をすることが可能です。
-
(2)離婚調停
話し合いでの離婚が難しい場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。
調停を申し立てずに、裁判で離婚したいという方もいますが、いきなり離婚裁判に進むことはできません。離婚調停を経て初めて、離婚裁判を提起することができます(調停前置主義)。
離婚調停では、調停委員が妻と夫の両方から話を聞き、双方が合意するよう調整し解決を図ります。
調停でお互いが合意すると、双方が合意したことが調停調書に記され、確定判決と同じ効力を発揮し、離婚が成立します。 -
(3)離婚裁判
協議離婚や調停でも離婚できなかった場合は、離婚裁判を提起することができます。離婚裁判は、終結するまでに1年以上かかることが一般的です。
裁判で離婚について争う場合は、民法第770条により、下記の法定離婚事由に該当している必要があります。- 不貞行為
- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
- 生死が不明(3年以上)
- 配偶者が、回復の見込みのない強度の精神病
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由
「夫の存在自体が嫌」「夫と一緒に暮らしたくない」「夫といるとストレスがたまる」といった漠然とした理由では、裁判で離婚を認められることは難しいでしょう。
お問い合わせください。
3、相手が離婚に応じてくれない場合の対処方法
夫が離婚に応じてくれない場合には、我慢し続けるしかないのでしょうか?
次に、講じるべき対策について解説します。
-
(1)相手と少しの間距離を置く
夫の言動や存在がストレスとなっているのか、もしくはそうなってしまった原因に法定離婚事由が該当していないかなどを冷静に考え、気持ちを整理してみましょう。
専業主婦の場合や仕事に活かせる資格がない場合には、就職するにあたって求められている資格を知り、資格取得のために必要なお金について計算しておくことも必要です。
離婚後の収入源や住まいなど、夫と離婚してからの生活についても具体的に考えてみましょう。 -
(2)別居をする
離婚調停などを目指して別居する場合には、相当長い期間(目安として、最低でも2年以上)別居状態を続ける必要があります。
長い期間別居状態にあり、お互いの夫婦生活が破綻していると認められれば、法定離婚事由の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高くなり、調停もスムーズに進みやすくなるからです。
ただし、別居にはリスクがあります。
夫の同意なしに別居することによって、夫婦の同居義務違反とみなされて「悪意の遺棄」として、逆に夫から慰謝料を請求される可能性があります。
そのため、別居をする場合は事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
●その他別居中の注意点
妻が夫よりも収入が多い場合には、夫から婚姻費用分担(お互いが社会通念上の「生活」を送るために必要な生活費)を請求される場合があります。
また、別居中に他の男性と関係を持ってしまうと不貞行為とされる可能性もあり注意が必要です。
※婚姻関係が破綻している場合には慰謝料などの支払い義務は生じないとされていますが、ケースごとに異なります。
4、離婚の相談を弁護士にするメリット
妻が夫の存在にストレスを感じ、離婚を考えているケースでは、妻や女性を見下した言動が多く、妻に依存している男性は少なくありません。
そのため、話し合いで離婚しようとしても、妻が夫に言いくるめられてしまい、不本意な離婚となってしまうケースも少なくありません。
しかし、第三者である弁護士が介入することにより、お互いが顔を合わすことなく、冷静に交渉を進めていくことが可能になるというメリットがあります。
さらに、不貞行為やモラハラ発言の証拠の集め方などを相談することもできます。
また、別居中の婚姻費用や離婚にともなう財産分与、養育費、親権など、法的な知識がある弁護士が介入することで、交渉がスムーズに進む可能性があるというのも大きなメリットと言えるでしょう。
5、まとめ
妻に「旦那がストレスなので離婚したい」と考えさせてしまう言動を繰り返す夫は、妻や女性を見下している言動が多い反面、妻に依存しているケースが多い傾向があります。
話し合いで離婚しようとしてもうまく話がまとまらず、もつれてしまうケースも少なくありません。
離婚を検討している場合は、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスへご相談ください。離婚や男女問題について経験豊富な弁護士がサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています