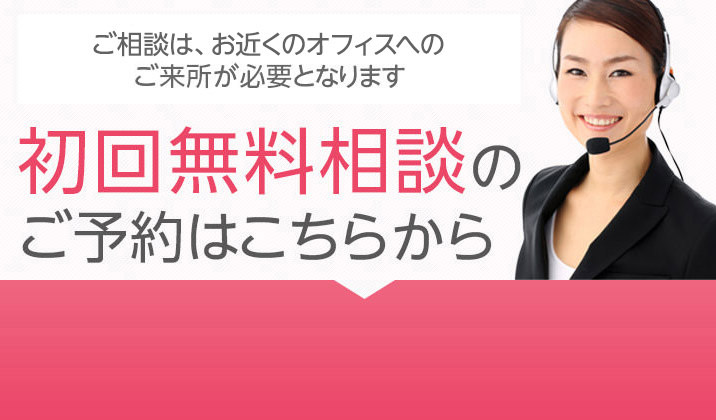家を出て行った配偶者が離婚を拒否! 婚姻費用を払い続ける必要はある?
- その他
- 婚姻費用
- 離婚しない

北海道北見市の女性が、離婚成立後に未払いの婚姻費用を求めて争っていた事件で、札幌高裁は、離婚によって未払いの婚姻費用請求権は消滅したと判断していました。
しかし、令和2年1月23日に最高裁が札幌高裁の判決をくつがえし、「当事者が離婚したとしても婚姻費用分担の請求権は消滅しない」との判断を下しました。
このような判断が下るのは初めてのことで、今後の離婚や婚姻費用に関する裁判実務にも影響を及ぼしそうだということです。
妻が家を出て行ったあとに離婚を拒否していながら婚姻費用の支払いを求め続けているようなとき、婚姻費用を支払い続ける必要はあるのでしょうか。また、支払わなかったらどうなってしまうのでしょうか。
本コラムでは、家を出て行った妻に対して婚姻費用を支払い続ける必要性や、別居している妻との離婚方法について、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスの弁護士が解説します。


1、そもそも婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るときに必要となるすべての費用のことをいいます。
食費や日用品代はもちろん、住居費、水道光熱費、子どもの教育費、医療費など日常生活にかかるあらゆる費用がこの婚姻費用に含まれます。
-
(1)だれが婚姻費用を払うべき?
法律上、婚姻費用は夫婦それぞれの経済力に応じて分担する義務を負っています。これは、民法上の相互扶養義務のひとつ、「夫婦はお互いに同程度の生活をさせなければならない」とする生活保持義務に由来しています。基本的には、収入の多い方から、少ない方へ毎月の生活費を渡すことになるでしょう。
夫婦が同居しているうちは、婚姻費用について問題になるケースはさほど多くはありません。しかし、別居を始めると婚姻費用の分担が問題になる可能性があります。
夫婦が別居すると、別々に生計を立てて暮らすことになるのが一般的です。ただし、夫婦の一方がこれまで専業主婦(夫)で無収入だった場合や、パート収入のみしかなかった場合は、別居によって生活費が不足してしまうケースが多々あります。そのようなとき、収入の少ない方は生活保持義務に基づき、収入の多い方に婚姻費用を請求できるのです。 -
(2)婚姻費用は離婚成立まで支払う必要がある
婚姻費用は、婚姻費用分担調停を申し立てたときから婚姻期間が続いている間はずっと支払い続ける必要があります。
それは、たとえ離婚に向けて別居していて、復縁することはありえないとしても同じです。理不尽だと思う方もいるかもしれませんが、正式に離婚が成立するまで、夫婦には生活保持義務があるため、婚姻費用を支払い続ける義務があるといえます。 -
(3)婚姻費用を支払わないとどうなる?
収入の多い方(たいていは夫)が、少ない方(たいていは妻)に婚姻費用を支払わない場合は、強制執行によって、給与や預貯金などの資産が差し押さえられる可能性があります。
給与の場合は、通常の金銭債権であれば4分の1までしか差し押さえができませんが、婚姻費用の場合は特別に2分の1まで差し押さえることができます。そのため、婚姻期間が続いている以上、きちんと婚姻費用を払い続けたほうがよいでしょう。
2、婚姻費用の金額の決め方とは
婚姻費用の決め方に関して、当事者の合意によって決める場合、特に法律上のルールはありません。そのため、以下の流れで金額を決定するケースが一般的です。
-
(1)基本的に夫婦の話し合いで決める
夫婦間の婚姻費用の分担割合をどれくらいにするかは、基本的には当事者間の話し合いで決めます。
話し合いで決められない場合は、裁判所のウェブサイトに示されている婚姻費用の算定基準を目安に決定するのもひとつの手です。なお、生活費はそれぞれの家庭事情によって大きく異なるものです。この算定基準より多くても少なくても、当事者同士が納得して決めたのであれば問題ありません。 -
(2)調停の場合、婚姻費用は算定表を基準にされる
婚姻費用分担調停の場合、婚姻費用は算定表を基準に計算されます。算定表とは、簡易迅速に婚姻費用の計算に行うため、裁判所が公表している早見表です。
婚姻費用は、原則として、夫婦の収入と子どもの人数・年齢で決まります。ただし、家賃やローンの支払いをどちらが行っているか、家にはどちらが住んでいるか、特別な教育費がかかっているかなどの事情によって、婚姻費用の分担は調整されます。
具体的に、どれくらいの婚姻費用が請求されるのかについては、裁判所のウェブサイトにある算定表で確認してみましょう。 -
(3)婚姻費用のシミュレーション
裁判所のウェブサイトに掲載されている婚姻費用の算定表を使って、実際に婚姻費用がどれくらいになるかをシミュレーションしてみます。ここでは、夫が会社員で年収400万円、妻がパート勤務で年収98万円あるとします。
子どもの人数・年齢によって、婚姻費用の支払金額が異なることになります。子どもの人数 婚姻費用の支払金額(月額) 夫婦のみの場合 4~6万円 14歳未満の子どもが1人いる場合 6~8万円 15歳以上の子どもが1人いる場合 6~8万円 14歳未満の子どもが2人いる場合 8~10万円 15歳以上の子どもが1人、14歳未満の子どもが1人いる場合 8~10万円 15歳以上の子どもが2人いる場合 8~10万円
なお、ベリーベスト法律事務所のウェブサイトで公開している婚姻費用計算ツールでは、ご家族の状況や年収を入力するだけで、婚姻費用の概算が簡単に算出できます。ぜひご活用ください。
-
(4)一度決めた婚姻費用は減額できる?
経済状況の変化によって、婚姻費用を支払う方の収入が減った場合、婚姻費用減額調停を申し立てることで、婚姻費用の減額を求めることは可能です。
しかし、現実的には、婚姻費用の減額が認められる可能性は低いかもしれません。
過去の裁判例でも、婚姻費用の減額ができるのは「調停や審判が確定したときには予測できなかった後発的な事情の発生により、その内容をそのまま維持させることが一方の当事者に著しく酷であって、客観的に当事者間の衡平を害する結果になると認められるような例外的な場合に限る」との判決が下されています(東京高等裁判所平成26年11月26日判決)。
お問い合わせください。
3、別居中の離婚を拒否する配偶者と離婚できる条件
別居がずっと続いていて復縁の可能性がないのであれば、婚姻費用を払い続けるより、いっそのこと離婚したいと考える方も多いでしょう。しかし、別居している配偶者と離婚できるかどうかは、別居している期間や離婚理由が考慮されます。
-
(1)性格の不一致などの場合
司法統計によれば、令和4年度の離婚理由で男女ともにもっとも多かったのが、「性格が合わない」でした(※)。性格の不一致には、「金銭感覚が合わない」「政治・宗教についての価値観が合わない」などがあります。
※ 裁判所「第19表 婚姻関係事件数別―申立ての動機別申立人別―全家庭裁判所」
しかし、性格の不一致を理由に離婚をしたいと思っても、相手方が「離婚しない」と主張している場合は、別居期間が相当長くなければ認めてもらいにくいのが実情です。
ケース・バイ・ケースですが、別居期間が5年程度以上であれば、離婚を認めてもらいやすいでしょう。別居期間自体が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚原因に該当するからです。
ただし、別居前に激しく争うなど、すでに夫婦関係が破綻していると認められる場合は、もう少し短い期間でも離婚が認められる可能性があります。 -
(2)相手の不倫や悪意の遺棄、DVがあった場合
配偶者に不倫や、悪意の遺棄、DVなどがあった場合、別居後まもない時期でも離婚が認められる可能性があります。
具体的には、相手に不倫されたことが耐えられなくて家を出た場合、相手が行方も告げずに家を出ていき長期間にわたり生活費も渡さなかった場合、相手からの暴力や暴言から逃れたいあまりに別居した場合などです。 -
(3)自分が有責配偶者の場合は離婚請求が難しい
自身が不倫をしたり、配偶者にDVをしたりしていたなど、自ら離婚原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
有責配偶者の場合、離婚訴訟において、離婚請求が認められることはとても難しいのが実情です。日本では、有責配偶者からの離婚請求は、厳しい要件を満たした場合のみ、認められています。
これは、有責配偶者からの離婚請求に対し、相手が「離婚しない」と主張しているときに、有責配偶者から離婚訴訟を提起した場合、裁判所の判決では離婚できないということです。
離婚協議や離婚調停で離婚を求め、相手が離婚を受け入れてくれるのであれば、離婚することはできます。
なお、別居中に有責配偶者から離婚請求をする場合、一般的には別居期間が10年程度ないと、判決によって離婚することは難しいでしょう。
4、別居を理由に配偶者と離婚する方法
別居中に離婚したいと決断したら、配偶者に離婚を切り出して離婚手続きを進めましょう。相手が離婚を拒否していて話を前に進められないときは、弁護士に相談して力を借りるのもおすすめです。
-
(1)まずは話し合う
別居を理由に離婚を進めるには、まず相手方と話し合いの場を設ける必要があります。話し合いの場では、婚姻費用のみならず、財産分与や養育費、子どもの親権、面会交流、必要であれば、慰謝料についても決めておいたほうがよいでしょう。
相手が離婚を拒否している場合は、解決金名目として財産分与を多めにしたり、持ち家を譲渡したりと、相手方にとって有利な条件を提示することで、離婚を受け入れてくれる可能性があります。
当事者同士だけで、離婚に向けた話し合いが難しいときは、弁護士のサポートを受けた方がよいでしょう。弁護士が、依頼者の代わりに、相手とコンタクトを取って粘り強く協議を進め、有利な条件をうまく引き出して、離婚に関する合意を取りつけられるケースは少なくありません。 -
(2)離婚調停を申し立てる
相手方がどうしても離婚を拒否していて、話し合いができないときは、離婚調停に持ち込むというのもひとつの手です。
離婚調停とは、家庭裁判所で裁判官と有識者などから成る調停委員を介して、相手と離婚等について話し合うことです。離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、相手方が遠方に住んでいる場合は、電話会議などを使って遠方にいながら協議を進めることもあります。
離婚調停では、調停委員に対して離婚したい理由を主張することになり、弁護士がついていれば、調停に同席して話し合いが有利に進むようにサポートしてもらえます。
調停が成立すると、合意した内容をもとに、調停調書が作成され終了となります。
一方で、相手が離婚しないとする姿勢を崩さない場合や、相手が裁判所に出頭しない場合は離婚調停不成立となり、それでも離婚を求めたいときには、離婚訴訟を提起する必要があります。 -
(3)離婚訴訟で争う
離婚調停が不成立の場合、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、離婚したい原因が、民法上認められている離婚事由に該当するかどうかについて問われます。また、証拠も必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。
裁判となると自力で争うことは難しいため、できるだけ早いタイミングで弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
離婚を考えた早期の段階で弁護士に相談しておくと、裁判になったときに必要な証拠についても、アドバイスを得ることができます。また、裁判の日には代理人として裁判所に出廷し、離婚したい理由が民法上認められている離婚事由に該当するかについて論理的に主張を展開してもらえるため、有利な判決を得られる可能性が高くなるでしょう。
5、まとめ
家を出て行った配偶者が離婚に応じてくれない場合、この先どうしたらよいのか困ってしまう方は少なくありません。
相手が無収入の場合やパート収入しかない場合は、生活費の心配があり、婚姻費用がもらえなくなることを恐れて、離婚を拒否している可能性があります。
しかし、収入が高く婚姻費用を支払う側からすると、別居がこの先もずっと続くのであれば、婚姻費用を払い続けるよりも離婚したほうが経済的メリットは大きいといえるでしょう。
別居している妻と離婚したいのに拒否されてお困りのときは、ベリーベスト法律事務所 札幌オフィスへご相談ください。離婚問題の知見・経験豊富な弁護士が、相談者の方の状況をヒアリングした上で最適なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています